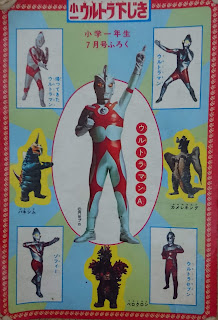ソニーのステレオラジカセ・愛称ナシ編

ラジカセには様々な愛称がつけられている。 ソニーならジルバップ、ジィーゼット、エナジー、ドデカホーン、ソナホークなどなど。 我々消費者も、型番だけより愛称があった方が覚えやすい。 だが愛称のないラジカセもある。 たいていは安いラジカセなのだが、時折高くても名無しのラジカセがある。 なぜだろうか。 そんなちょっと高い、あるいは結構高いのにブランドのないソニーのステレオラジカセを集めてみた。 WA-8000 49,800円。 短波の聞ける録音再生型ウォークマンみたいな機種。 本体のスピーカーはモノラルだが、ヘッドホンで聞くとステレオになるのだ。 でもウォークマンの名前もついていないし、録再型だからといってプレスマンの名もなし。 ワールドワイドウォークマンとかと名付けたらどうだろう。 当然弟機のWA-にも愛称はない。 CFS-9000 74,800円 この値段なら愛称があってもよさそうなものだがなし。 当然弟機のCFS-7000、44,800円にもなし。 であるから更に弟機のCFS-5000、32,800円にもない。 兄にないのに弟にあるのはおかしいからねえ。 ラジカセというよりコンポっぽいデザインだ。 CFS-W900 89,800円 CFS-9000の進化版みたいなステレオラジカセ。 進化しても名前はない。 Wの名の通りダブルカセットだ。 CFD-5 108,000円 ソニーのステレオラジカセで、CDを初めて搭載した機種、それがCFD-5だ。 この機種のベースになったっぽいCFS-7000にも愛称がなかった。 ソニーのポータブルCDプレーヤーD-50も愛称がなかった。 ディスクマンと名付けられるのはD-50Mk2からだ。 つけないのはこの頃の方針なのか。 CFD-W888 108,000円 CFD-5の後継機種。 ダブルカセットになったが値段は据え置き。 名前はまだない。 WカセットにはWキッドという愛称があったが、これはデカくてキッドじゃないのだね。 平成になり、ドクターチェンジャーの後はこれといった愛称はなしだ。 あっても良さそうなのだが。 名前をつけるコストをカットしていたのだろうか。 名前は考えなきゃいけないし、ロゴも作らなければいけないし、色々考...